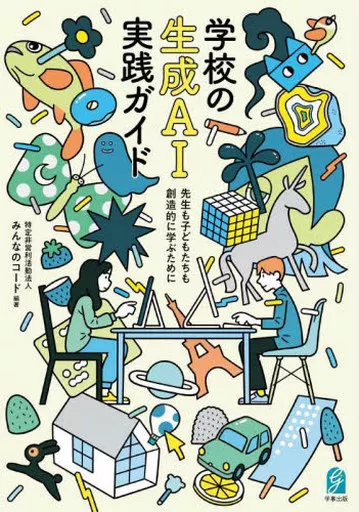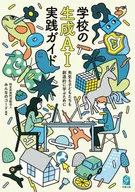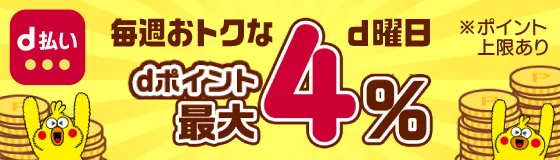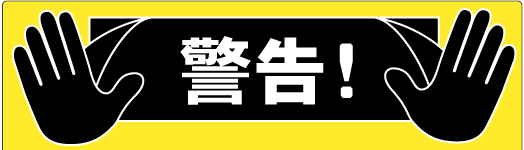単行本(実用) <<教育>> 学校の生成AI実践ガイド / みんなのコード
備考
教育
【内容紹介】
生成AIの基本から実践までがこの1冊でよくわかる!
文章や画像を自動で作り出す「生成AI」は、近い将来、これからの教育のあり方を変えていく大きな可能性を秘めています。
本書では、学校で生成AIを使い、創造的な学びを広げていくために必要な知識、理論をギュッと収録。さらに実際に学校で行われた先進的な事例も紹介。「そもそもAIって何?」「どうやって学校で使えるの?」「全く知らなくて子どもたちに教えられない……」等々--そんな先生たちの疑問、悩みすべてに答え、実践を後押しする1冊です!
【目次】
まえがき
第1章 「生成AI」って何?
1 「生成AI」を知る
2 生成AIの特徴と仕組み
3 生成AIの得意・不得意
4 生成AIの懸念点
5 現在と今後の普及状況
Column(1) 生成AI の安易な活用はNG!?
第2章 「生成AI」は学校教育とどう関わるの?
1 生成AI と教育に関する国の方針(ガイドライン)
2 学校現場における生成AIとの向き合い方
3 生成AIが学校現場に与える影響
4 教育は生成AI を通してどう変わる?
5 子どもたちに身に付けてほしい「情報活用能力」
6 発展途上のAI技術
Column(2)中学校1年生、夏休みの宿題に生成AIを使ってみる
第3章 「生成AI」を学校でどう活用する?
1 生成AI導入編:授業で使うツールを準備しよう
2 生成AI実践例(1):授業での使い方
3 生成AI実践例(2):校務での使い方
4 小学校の導入事例:千葉県印西市立原山小学校(6月13日)
5 中学校の導入事例:石川県加賀市立橋立中学(5月12日)
6 高等学校の導入事例:鹿児島県立奄美高等学校(8月24日)
Column(3) 高校の課題ではより高度な生成AI活用を!
特別寄稿
生成AIで求められる教育の「再定義」小宮山 利恵子
生成AI を「よりよく使う」ために 島谷 千春
教育に携わる人こそ生成AIと向き合い、活用を 神野 元基
資料(1) 初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン
資料(2) 「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」への見解
【著者略歴】
「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」を基本理念に掲げ、2015年に設立された特定非営利活動法人。プログラミング必修化を機に活動を加速させ、学校教育にも様々な場面で関わっている。代表理事は利根川裕太。