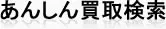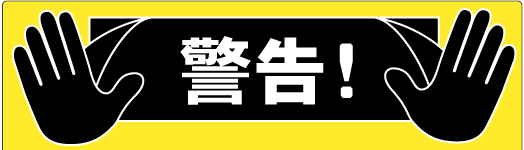教育
【内容紹介】
いつの時代も変化に満ち、先行き不透明だからこそ…
私たち教師は、正解のない「問い」に、納得できる「答え」を見つけられる子どもを育てていく必要があるのではないでしょうか?
本書の概要
本書は3章構成で、まず第1章では、正解のない「問題」に子どもたちが「答え」を見つけるとはどのようなことなのかを概説します。
続く第2章では、「授業づくり-10の常識の嘘」と題し、これまでは通用してきた考え方、思い込みから子どもの実態とかけ離れてしまっていた方法など、10の常識の嘘を取り上げながら、教師としての新たなマインドセットを行うために必要なことについて述べています。
最終章である第3章では、脳死と臓器移植という「死」と「生」に向き合う「いのちの授業」の実際を紹介します。
本書からわかること
1.正解のない「問い」とは何か? そうした「問い」に、なぜ正対する必要があるのかがわかる
これから先は先行き不透明な時代が到来すると言われます。
しかし、果たしてそうでしょうか?もし、こうした論が正鵠を射ているのだとしたら、かつて「先行き透明な時代」なるものがあったはずです。
しかし、そんな時代な存在したことがあったのでしょうか?
本書では、「コミュニケーション能力」「キー・コンピテンシー」「道徳教育」「哲学」といった切り口から、教育現場は何に着眼し、どのような学びをつくっていけばよいかについて述べます。
2.「授業づくり-10の常識の嘘」がわかる
本書では、以下に挙げる10の常識の嘘を取り上げ、どのようにして、そうした嘘を克服していけばよいかについて紹介します。
[常識の嘘(1)]むずかしくして深く考えさせることの嘘
[常識の嘘(2)]子どもの言葉を要約して板書することの嘘
[常識の嘘(3)]話型指導の嘘
[常識の嘘(4)]最後まで話を聞く子どもを育てることの嘘
[常識の嘘(5)]丁寧に、繰り返し、ゆっくりと話すことの嘘 他
3.「いのち」の大切さを学ぶとはどのようなことかがわかる
本書では、医師とも連携し、理科、保健学習、総合学習、道徳を通じて「脳死」と「臓器移植」を扱った「いのちの授業」を紹介しています。
この授業を行うためには、「死」というものとどう向き合うかについて学べる学習が必要となります。
しかし、学習指導要領から逸脱した実践ではありません。
学習指導要領に規定する各教科等の「内容」や「内容の取扱い」に基づいて行った実践(配慮事項はあるものの、どの学校においても行える実践)です。
授業で直接的に「死」を扱うのは、(たとえ制度上問題がなかったとしても、心情的に)ためらう気持ちもあるでしょう。
しかし(「死」に限らず)教師が心理的抵抗感を覚える対象のなかにこそ、(教育的吟味は欠かせませんが)子どもたちのよりよき成長に資する「学びの可能性」があるのです。
【目次】
第1章 正解のない問題に「答え」を出す-共通了解可能性への挑戦
「コミュニケーション能力」から学ぶ
「キー・コンピテンシー」から学ぶ
「道徳教育」から学ぶ
1 友達からの手紙
2 ボランティア活動の動機
「哲学」から学ぶ
1 自由の相互承認
2 共通了解可能性
3 美意識
第2章 授業づくり-10の常識の嘘
[常識の嘘(1)]むずかしくして深く考えさせることの嘘
3割削ってちょうどいい
「附属だからできる」と言われる授業からの脱却
教師のリフレクション(授業中)
[ポイント1]教師の「発信」の事実から子どもの学習状況を読み取る
[ポイント2]授業展開の想定にこだわらない
教師のリフレクション(授業後)
[常識の嘘(2)]子どもの言葉を要約して板書することの嘘
不誠実な板書
視点展開できない子どもの実態
授業改善の視点
[視点1]討論にしない
[視点2]自分とは違う考えをもつ他者に視点転換させる
[視点3]実験結果の見通しを共有させる
[常識の嘘(3)]話型指導の嘘
話型指導の発想を転換する
低学年のスピーチ指導
1 スピーチ「3つの約束」
2 スピーチの準備
3 Aさんのスピーチ
話し言葉と書き言葉の質的な違い
[常識の嘘(4)]最後まで話を聞く子どもを育てることの嘘
話を最後まで聞かない子ども
授業ユニバーサルデザインへの誤解
国語や算数とは異なる理科授業の特性
話し合いながら観察・実験する
繰り返し実験できるようにする
1 五月雨式に実験をスタートさせる
2 グループを二つに分けて観察・実験できるようにする
[常識の嘘(5)]丁寧に、繰り返し、ゆっくりと話すことの嘘
子どもが嫌うNKO
1 N(ながい)話
2 K(くどい)話
3 O(おそい)話
映像を共有し、理屈を語る
全体を示し、部分を語る
1 目的地までの道順の説明
2 ダンスの練習に見る全習法と分習法
[常識の嘘(6)]教えずに考えさせる授業の嘘
新しい学力観の後遺症
「教えて考えさせる授業」への誤解
1 一連と二連を比較させて教える
2 子どもたちの理解度を確認する
3 理解深化課題で考えさせる
4 自己評価させる
入口は狭く、出口は広く
[常識の嘘(7)]事実を示し、子どもの考えを変えることの嘘
選択的注意
観察の理論負荷性
反証可能性
事実は理論を倒せない
[常識の嘘(8)]教科書をつかわないで授業することの嘘
教師が陥りがちな三つのタイプ
領域可能性
教科書をつかうとはどういうことか
教科書活用の二つの視点
[視点1]教師が教材研究を行うための教科書活用法
[視点2]子どもが予習・復習を行うための教科書活用法
[常識の嘘(9)]受信型評価の嘘
つかえない評価基準
「受信型」の評価
「発信型」の評価
[ポイント1]「相互評価」と「自己評価」とを関連づけて問題解決の場に組み込む
[ポイント2]問題解決場面で、教師が行った評価を積極的に子どもに還元する
[ポイント3]教師が「だれに、どんな指導をしたか」を、事後に洗い出す
必要条件としての「量的評価」
評価における教師の思考力・判断力・表現力
[常識の嘘(10)]問題解決学習の嘘
「問題解決学習」とは?
「問題解決的な学習」とは?
曖昧な「問題」「答え」との関係
「問題」の主語と述語の位置
変遷する「問い」
直接的に問う、間接的に問う
1 直接的に問う
2 間接的に問う
第3章 いのちの授業
臓器移植を扱う「いのちの授業」との出合い
小学校の学習における「死」の取り扱い
道徳の授業から得た授業づくりのヒント-切手のない手紙
理科「いのちの授業」づくり
理科「いのちの授業」の実際
1 人と動物の似ているところ
2 人の死の判定基準(その1・死の三兆候)
3 人の死の判定基準(その2・脳死)
4 4つの権利
総合学習(保健教育)「いのちの授業」の実際
1 総合活動(その1)「Sちゃんとわたしたち」
2 総合活動(その2)「Sちゃんの闘病~どうしてアメリカで移植手術を受けたのか」
3 授業を終えて
4 授業後:調べ学習「いのちの新聞」づくり
日本の「脳死・臓器移植」の歴史的経緯
1 和田心臓移植事件
2 「臓器移植法」の制定と改正の推移
日本における「臓器移植」の現状
医療と教育との連携
1 学んで救える子どもの命 PH Japanプロジェクト(日本小児循環器学会)
2 学会と教育の連携委員会(日本小児循環器学会・学術集会)
3 いのちの教育セミナー
4 いのちの授業づくりプロジェクト
【著者略歴】
筑波大学附属小学校校長。
1960年、福島県福島市生まれ。
北海道教育大学教育学部を卒業後、福島県立公立小学校を経て、筑波大学附属小学校教諭、筑波大学附属小学校副校長を経て現職。
日本初等理科教育研究会元理事長(現在顧問)
売りたい商品を検索し、売却カートへ入れてください

|
<<教育>> 正解のない「問い」に、納得できる「答え」を見つけられる子どもを育てる / 佐々木昭弘
買取価格1,200円
※在庫状況、更新のタイミング等により価格が変動する可能性がございます。
|
商品の詳細
| JAN | 9784491054513 | 管理番号 | BO4881348 | 発売日 | 2024/11/27 |
| 定価 | 2,310円 | メーカー | 東洋館出版社 | 型番 | - |
| 著 | 佐々木昭弘 | ||||
| カテゴリ | 本 ≫ 書籍 ≫ 教育・育児 ≫ 教育 |